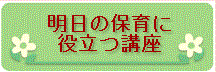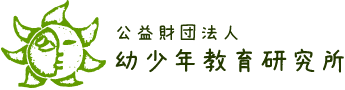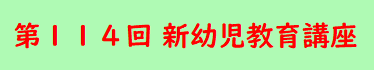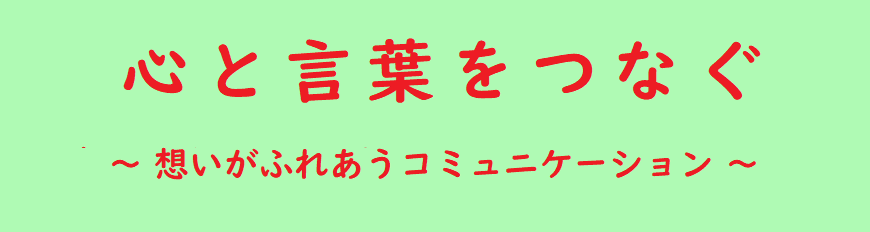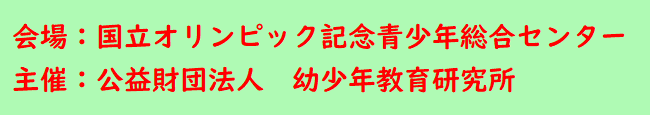第 1 1 4 回 新 幼 児 教 育 講 座

( 101回講座 )

( 102回講座 )
2024年 3月28日 ( 木 ) |
< 09 : 15 ~ 09 : 45 > 受 付 |
< 09 : 45 ~ 10 : 00 > 開 講 式 |
午 前 の 部 基 調 講 演 ( 全 体 会 ) |
< 10 : 00 ~ 12 : 00 > |
『 保育をゆたかに ~絵本でコミュニケーション~』 |
講 師 : 村 中 季 衣 学校法人 ノートルダム清心学園 ノートルダム清心女子大学 教授 / 児童文学者 ・ 児童文学作家 |
俯瞰図番号:E2 |
こどもとおとなが、ともに育ちあう場所は、絵本がいちばんいきいきするところ。 「こう選んでこう読めばうまくいく」というノウハウではなく、ちいさい人たちが自分のいのちに照らして絵本と結びあう瞬間について考えてみましょう。 |
< 12 : 00 ~ 13 : 15 > 昼 食 ・ 休 憩 |
午 後 の 部 前半 分科会 ( 4分科会から1つを選択受講 ) |
< 13 : 15 ~ 15 : 15 > |
☆ 分科会 A |
『 発達がわかると保育がおもしろくなる』 ~子どもを見つめ響きあう保育~ |
講 師 : 兵 頭 惠 子 公益財団法人 幼少年教育研究所 監事 現場保育者 : 喜 多 な な 子 学校法人 慶和学園 認定こども園 しらゆり 教諭 現場保育者 : 田 中 愛 弓 学校法人 池谷学園 冨士見幼稚園 教諭 |
俯瞰図番号:D1 |
4月からの新たな園生活、どんなドラマが始まるのでしょうか。現場の先生から子どもの姿や園生活など保育現場のリアルを語っていただき、参加の先生方と共に子どもの育ちを読み解いていきましょう。そして“現場100回?”を実践されていらした兵頭惠子先生に「子どもの理解と発達」や「保育がおもしろくなる秘訣」について語っていただきます。子どもを見つめた先にある響きあう保育を考えていきましょう。 *テキスト:『保育の事例で読み解く 3・4・5歳児の発達』(チャイルド本社 令和6年2月刊) |
☆ 分科会 B (フレッシュ講座) |
『 保育者として歩み出すために 』 ~ 豊かなことばが育つ保育 ~ |
講 師 : 安 見 克 夫 学校法人 東京成徳学 東京成徳短期大学 名誉教授 学校法人 安見学園 板橋富士見幼稚園 理事長・園長 : 大 澤 洋 美 学校法人 東京成徳学 東京成徳短期大学 教授 |
俯瞰図番号:C2 |
保育者は、ことばによる様々なコミュニケーションを求められます。子どもと保育者、保育者と保護者が豊かに関わり合うためには、どのような知識と意識が必要なのでしょうか。素敵な保育者になるために、仲間と一緒に学び合いましょう!
第1部では、ことばによるコミュニケーションについて安見克夫先生にご講義をいただき、第2部では、ことば遊びを楽しみながらことばの育ちを考えていきます。
|
☆ 分科会 C ( 中堅経験者( 推奨 )講座 ) |
『 保育ファシリテーション 』 ― 保育の質を高めるチームづくり ― |
講 師 : 矢 藤 誠 慈 郎 学校法人 和洋学園 和洋女子大学 人文学部 こども発達学科 教授 |
俯瞰図番号:B6 |
子どもの幸せな育ちのために、保育者が力を出し合いながら保育の質を高める組織文化を醸成していくことが大切です。この分科会では、この課題の解決に向けて、ファシリテーションに焦点を当てて考えていきます。 |
☆ 分科会 D ( 支援児教育講座 ) |
『 心が寄り添うインクルーシブ保育とは 』 |
講 師 : 守 巧 学校法人 宝仙学園 こども教育宝仙大学 こども教育学部 教授 |
俯瞰図番号:D3 |
どの子どもも大切にされ、集団で生活する心地よさを感じてもらいたいですね。そのためには、すべての子どもが過ごしやすい環境やわかりやすい保育が求められます。 心が寄り添えるインクルーシブな営み(保育)を具体的に考えていきます。 |
< 15 : 15 ~ 15 : 40 > 休 憩 ・ 移 動 |
午 後 の 部 後半 アトラクション ( 全 体 会 ) |
< 15 : 40 ~ 16 : 40 > |
☆ アトラクション |
『 絵本を読んでもらう喜び 』 |
講 師 : 聞かせ屋 。 けいたろう 絵本作家 / 講演家 |
俯瞰図番号:E2 |
絵本の最高の味わい方は、読み聞かせです。文章を読んでもらえば、絵をじっくり味わう時間が約束されるからです。本来、手の届く距離で読むのが理想ですが(笑)。
今日は絵本を映画のように、味わってもらいましょう。
|
< 16:40 ~ > 閉 講 式 |
● 本講座は、幼稚園・認定こども園版キャリアアップ研修に該当します。
● 当研究所は、全国47都道府県より「処遇改善等加算Ⅱに係る研修の実施主体」の認定を受けています。